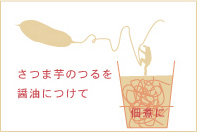第二話 小豆島醤油の歴史

(1) 小豆島での醤油の始まり
醤油が多くの人に馴染みだした頃、紀州湯浅の赤桐家が天正19年(1591)の春、大阪城建設中の太閣秀吉も醤油と米糧米を献上し「天下一の調味料」と激賞された記録が残っているけど、ちょうどその時、小豆島では全島に渡り大閣秀吉の大阪城築城の石材を切り出していたんだ。
その時、小豆島の人が紀州湯浅の醤油に興味を持って、湯浅で製造方法を教えてもらったのさ。そして天正末年〜文禄初年には醤油が造られたと言われているよ。でもね、この時の醤油はまだ醤の中に溜まった汁程度の物だったらしんだ。そこで「醤の汁」を「醤の油」にしたくって、一生懸命改良を重ねていったんだ。
(2) 小豆島で醤油が起こった理由
1、塩造りの有力な産地であったこと
そもそも小豆島では塩造りが盛んだったんだ。でもね、塩そのものでは収支が合わないんだ。そこで塩を材料とした加工業・醤油業に転換していったんだよ。


2、立地条件と海運業の発達
瀬戸内海東部にあって、海を渡れば商港堺や天下の台所大阪があるという、最も恵まれた立地条件だったんだ。
しかもね、当時は海運業がすごく盛んだったんだ。製品の海運輸送は陸上輸送と比べて、かなり有利だったんだよ。京都・大阪という大消費地近くだったことが小豆島醤油の発展の一番の要因さ。
3、九州との交流
古くから九州との交流をしてたんだ。そこで素麺や塩は九州へ移出して、醤油の原料である大豆や小麦は九州から移入してたんだ。 ちなみに、この関係は今でも続いているよ。


4、耕地面積の狭小
小豆島は山が少なく、耕地面積が少ないから、米穀の自給自足は不可能なんだ。
そこで塩や素麺を移出して、材料を他県から取り入れて造り、作った物をまた移出して生計を立てていってたんだ。醤油の移出、移入の文化もその一つだね。
5、島民の開放性・進取性
小豆島島民の目は常に海の彼方に向いてたんだ。時には倭冦の一員として中国や商戦の沿岸を馳駆した人もいたし、また時には島原の乱鎮定にも加子として出向してたんだ。
そして日常的に、近世の初めから塩廻船が大阪や九州と島の間を絶え間なく住来して、奥州や九州の諸大名の米や諸物資を江戸や大阪によく搬送したものさ。大阪城築城の石などをのせる石船も運行していたよ。
こうして小豆島の文化は他県の良さを島の良さに結びつけながら作られていったんだ。
塩の文化から醤油の文化へ転換するのも、島民の進取の気勢の現われだね。
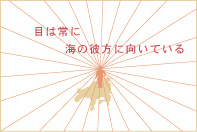

6、天領小豆島
江戸時代260年を通じて一時期、一部の地域を除いては小豆島は幕府の直轄地、つまり天領だったんだ。藩の奨励も保護、冥加金の上納もなく、比較的自由な支配の元にあったんだ。
新しく起こった農間企業について、格別な保護や規制も受けなかったことが島醤油を発達させる上で有利に働いたようだよ。
7、気候風土
小豆島の高温乾燥性と清澄な空気が、麹菌の発育や醤油諸味の熟成にとても適してたことが、醤油製造の上で有利に働いたよ。
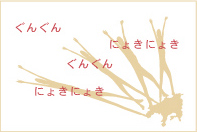
以上の諸条件が揃っていたことから、比較的遅い発達をしたのにもかかわらず、醤油の主産地の1つとされるようになったのさ。
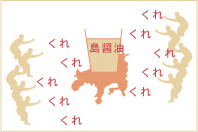
(3) 小豆島醤油が広がっていく
江戸時代末期になって、京都や大阪でも醤油需要が増えて、小豆島醤油の醸造石数が増加、万延年間(1860〜61)以降に、島の重要産物として広く宣伝されだしんだ。
さらに、明治維新による資本主義社会の波にのって目覚ましく発展して、明治11年(1878)以降から19年(1886)頃までの島の醸造家の数は約400戸に達し、その仕込石数は35,000石と、明治初年に比べ、倍増したのさ。
(4) 足場を固めていく
小豆島で醤油が盛んに作られるにつれて多くの問題も出て来て、地盤の固まっていない小豆島醤油は悪戦苦闘の繰り返しだったよ。
問題1つ目は400件ほどある醸造家の中の零細業者から粗悪な醤油を売り出すこともあったんだ。
その結果小豆島醤油の成果を落とす場合もあったんだよ。それではいけないってことで、小豆島の醤油の組合が、悪い醤油を売らないよう注意して島醤油の品位を確保したんだ。
問題2つ目は阪神両者との関係の調節だ。相手は強力な市場で働く大阪商人だったから商談は大変だったね。
問題3つ目は醤油税を払わなきゃいけなくなったこと。これは零細な醸造家にとっては大打撃で、次々と廃業していき、163件にまで減ってしまった。
最後、これはいいこと。日清戦争によって日本全体が景気よくなったんだ。醤油業界も同じで売れ行きがよくなって、 生産石数も大幅に増えたよ。もう香川県の7割り近い石数の醤油は小豆島醤油さ。
もう、良くなって来たんだから失敗したくない。小豆島醤油製造同業者組合を設立しよって製造法や材料の確保、 問屋との取引の合理化が強化していたのさ。
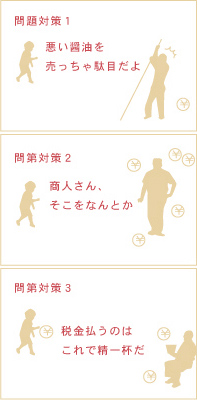

(5) 醤油醸造試験場の設立とその業績
小豆島醤油製造同業者組合が頑張ってもなかなか向上しなかったのが品質。
技術者を集めて改良案を出し合って、いくら機械化を図ってみても、いろんな実験をしてみても都会の品質と比べたら遥かに劣っていたんだ。
いくら島だけでやってもかなわない。そう思って県立醤油試験場を建てたいと県と話を進めていったけどそう簡単にはできなかった。
まずは「同業組合醸造試験場」が苗羽村に建てられ、2年後には「小豆郡立醸造試験場」になって、その3年後に「県立工業試験場」となることができたんだ。試験場が築き上げられてからは科学技術も機械も設備も磨きをかけ、島の醤油の質をあげていくことができたのさ。
(6) マルキン醤油
日露戦争後、日本は資本主義社会の躍進期だった。
小豆島の醤油業者が土台を固めていくうときの中で特に注目すべきはマルキン醤油株式会社の設立だよ。
小豆島の醤油は試験所のお陰で品質が高まっていったんだけど、関東醤油に匹敵する最上醤油を作るためには、小資本による個人企業ではその目的を達成できない。
そこで島の醤油業者を集めて協議会を開き、小豆島醤油100年の大計のため関東の最上醤油と並び、称される良質の醤油を作って販売しようとマルキン醤油を設立することにしたんだ。
そこでマルキンでは醸造試験場の科学的効果を完全に利用して品質を上げていくとともに、軽く見られがちだった広告宣伝にも力を注いだんだ。
その後、醤油業界の競争の荒波にのまれながらも約30年ほど後、関東のキッコーマン・ヤマサ・ヒゲタ3印に加えて、4印メーカーとして評価されるようになったよ!
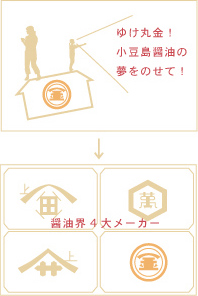
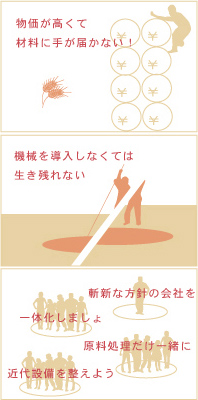
(7) 第二次世界戦後の機械化との戦い
敗戦後、経済界は混沌としてインフレーションによる諸物価高騰が激しくって、醤油業界も原料の入手が難しかったから、戦時中以来使用され始めた化学醤油製造に頼らざるを得ず、従来の本醸造製造醤油は一時姿を消しちゃったんだ。
機械導入が推薦されていったことと競争が激しかったことから、価格は下がっていき、機械を導入できない小豆島の小さな醤油業者は生き残りにくくなっちゃった。そこで品質向上・後継者確保・省力化等を目指して資本を出し合って主に麹作りを目的とした機械を導入した会社を建てて、原料処理を一緒にし、その後はそれぞれで製麹して醤油を作っていったのさ。
また、島の大手の醤油業者も島の醤油の強くしようとしてマルキン醤油と合同していったんだ。その後、大手が抜けたことによって体制が弱くなることを防ぐために、「タケサン」を設立したよ。
「タケサン」は「醤油屋は調味料屋」との基本方針のもと、多角化路線を取って、様々な企業努力を重ねながら島の最大手企業として今に至っているよ。
また、「タケサン」が中心となり、8社の加盟のもと近代設備の共同向上「島醸」を丸金醤油の跡地に設立して、島の醤油の強い土台を作り上げていったよ。
(8) 佃煮製造業
太平洋戦争後、敗戦によって人々の心が疲れていた上に、極端な物資不足、ことに食糧事情の悪化は甚だしいもんだった。
島内の醤油業も、戦中戦後の原料不足のため、すぐに正常の生産量にまでは回復しなかったんだけど、産地として若干の余裕もあったから、醤油を利用して少しでも食生活の充実を計ろうとしたんだ。